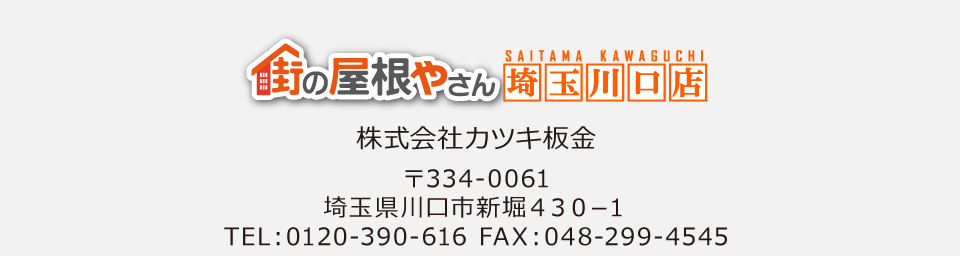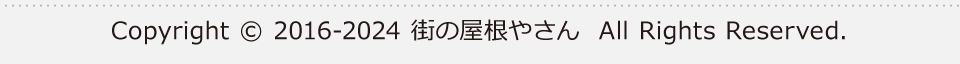2025.09.18
こんにちは!日本一の板金屋を目指している「街の屋根やさん川口店」です💛今回ご紹介するのは、埼玉県蓮田市で行った貫板交換と一部棟板金交換工事の事例です。屋根の棟板金(むねばんきん)は、雨風の影響を受けやすい部分で、劣化が進むと雨漏りや飛散といった大きなトラブルにつながることもありま…
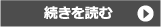
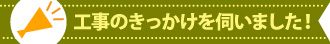
川口市にお住まいのA様より、「屋根の板が浮いて見える」とのお問い合わせをいただき、現地調査を実施したところ、棟板金(むねばんきん)を固定するための貫板(ぬきいた)が劣化していることが判明しました。
まずは屋根に上がり状態を確認しました。棟板金を留めている釘が浮いていたり、外れていたりしており、強風が吹いた際には飛散する恐れがありました。
棟板金の下にある「貫板」は、板金を固定する土台のような役割を担う重要な部材です。今回使用されていた貫板は木製のもので、経年劣化により変色が進行し、雨水を吸って腐食しかけている状態でした。これでは釘が効かず、台風時などに棟板金が剥がれるリスクがあります。






工事当日はまず既存の棟板金を丁寧に取り外し、劣化した木製の貫板を撤去します。
木の内部はかなり傷んでおり、一部は手で軽く押すだけでへこむほどでした。ここまでくると、自然災害が来る前に交換できて本当によかったと思える状態です。

撤去作業の後は、いよいよ新しい樹脂製の貫板を取り付けます。
材質が軽くまっすぐなため、施工もしやすく、ビスでしっかりと固定できるため、強風時にも安心です。
新しい貫板を取り付けた後、棟板金も再設置し、シーリング材(防水用のゴムのようなもの)で仕上げます。
雨水の侵入を防ぐための重要な工程です。


貫板には大きく分けて**「木製」と「樹脂製」**の2種類があります。それぞれに特徴があり、状況に応じて選ばれます。
木材で作られた貫板は、昔から一般的に使用されてきました。加工がしやすくコストも比較的安価で、職人にもなじみのある素材です。
【メリット】
材料費が比較的安い
加工しやすく施工しやすい
【デメリット】
雨水や湿気で腐食しやすい
釘やビスがゆるみやすく、台風などで棟板金が飛びやすくなる
定期的な点検・交換が必要(耐用年数10年程度)
樹脂(プラスチックのような素材)を主成分とした貫板は、木の弱点をカバーするために開発された耐久性に優れた新素材です。近年ではリフォームや新築の現場でも採用が増えています。
【メリット】
腐食しにくく、シロアリ被害の心配もほぼない
湿気や気温の変化で反りにくい
ビスがしっかり効くため、風で棟板金が飛ぶリスクを抑えられる
耐用年数が長く、メンテナンス頻度が少ない
【デメリット】
木製に比べて材料費が高め
重量は軽いが、硬くてやや加工しづらい面がある(施工には慣れた職人が必要)

施工完了後には、屋根全体がしっかりと固定され、見た目も引き締まりました。
A様からも「これで安心して台風シーズンを迎えられる」とのお言葉をいただき、私たちもとても嬉しく感じました。
貫板は屋根の表面からは見えにくいため、劣化に気づきにくい部分です。
しかしながら、屋根全体の耐久性に関わる重要な部材のため、10〜15年に一度は点検・交換をおすすめしています。
当社では川口市を中心に、屋根の無料点検も承っております。
「ちょっと気になる」「前回の工事から時間が経っている」など、お気軽にご相談ください!
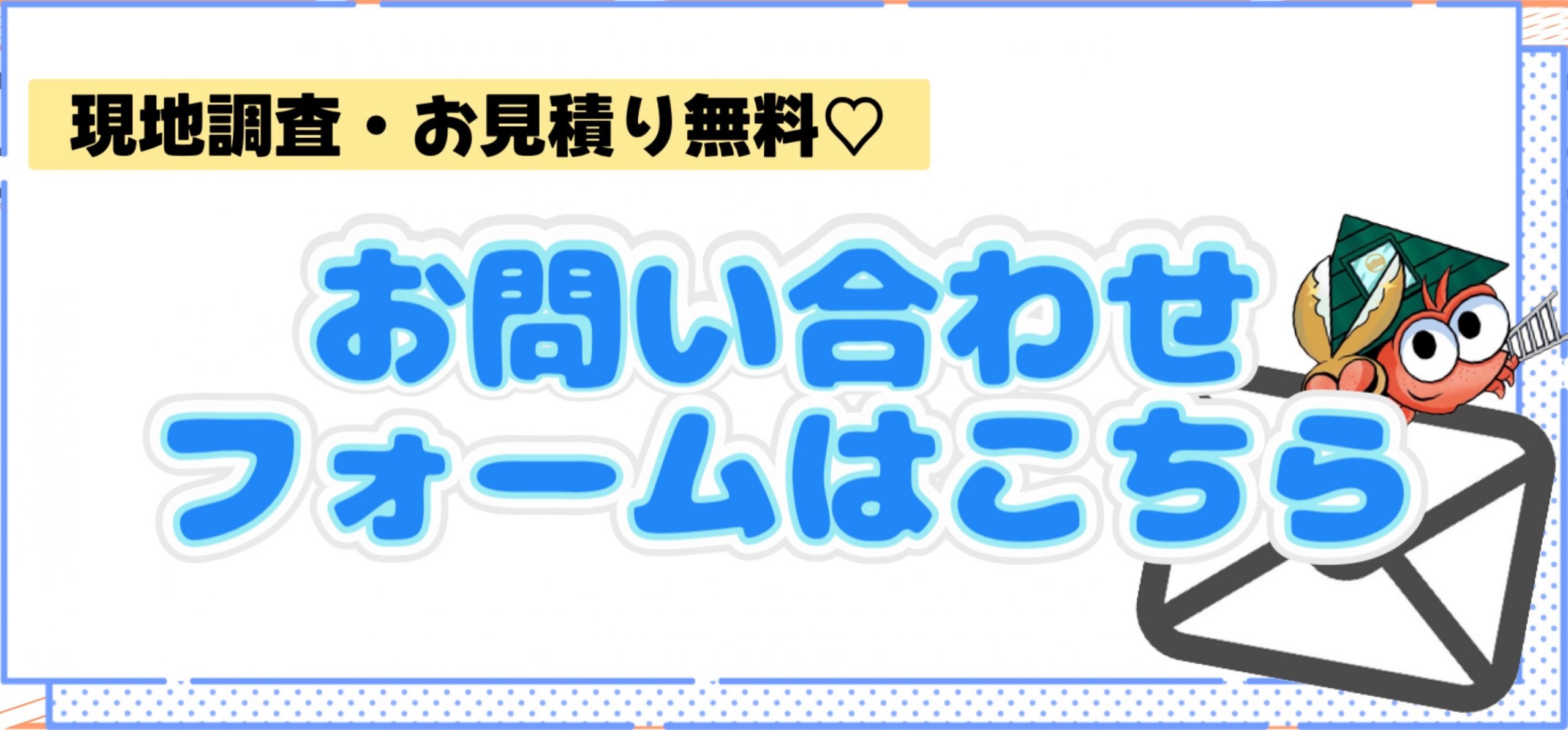
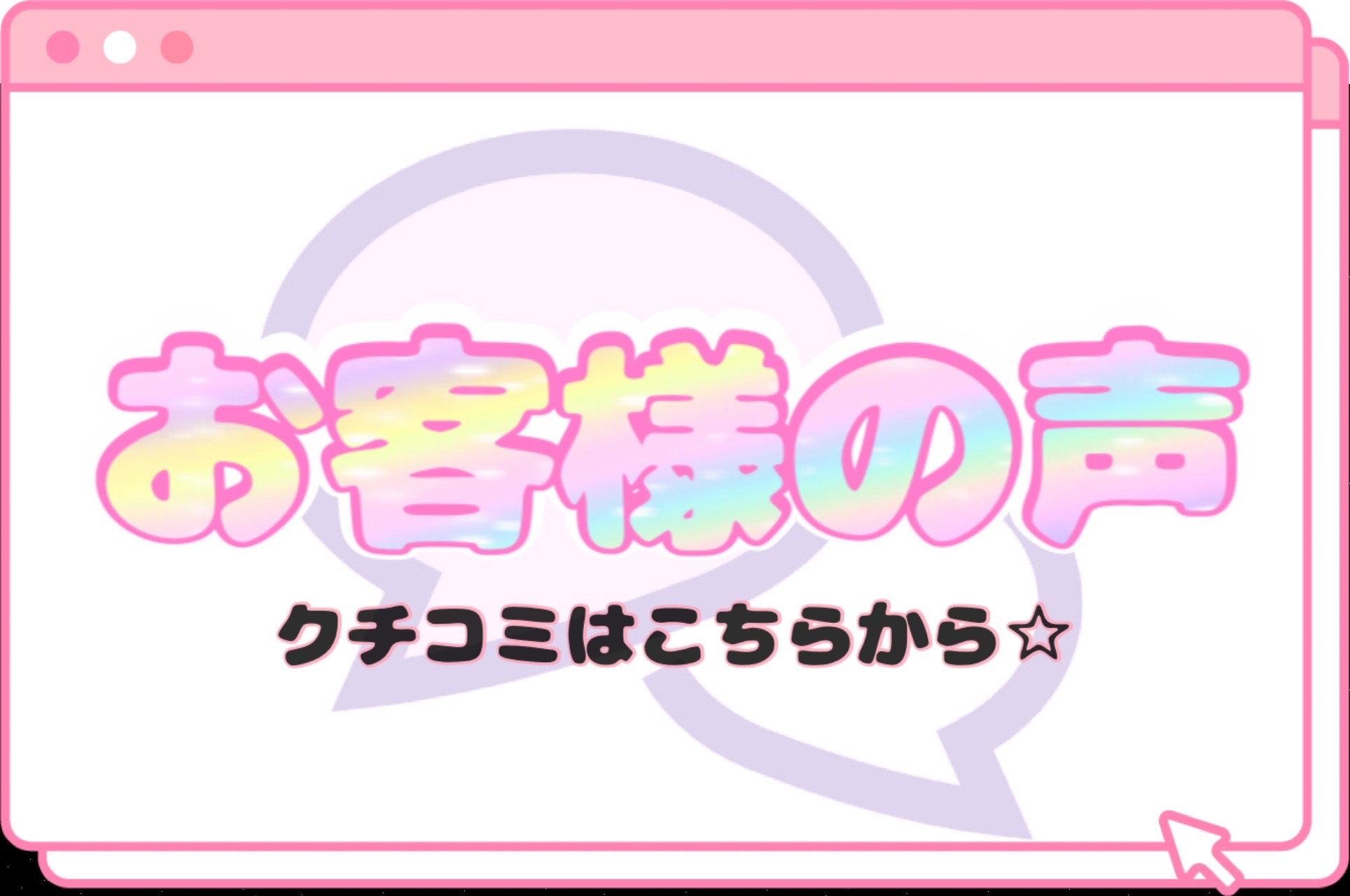
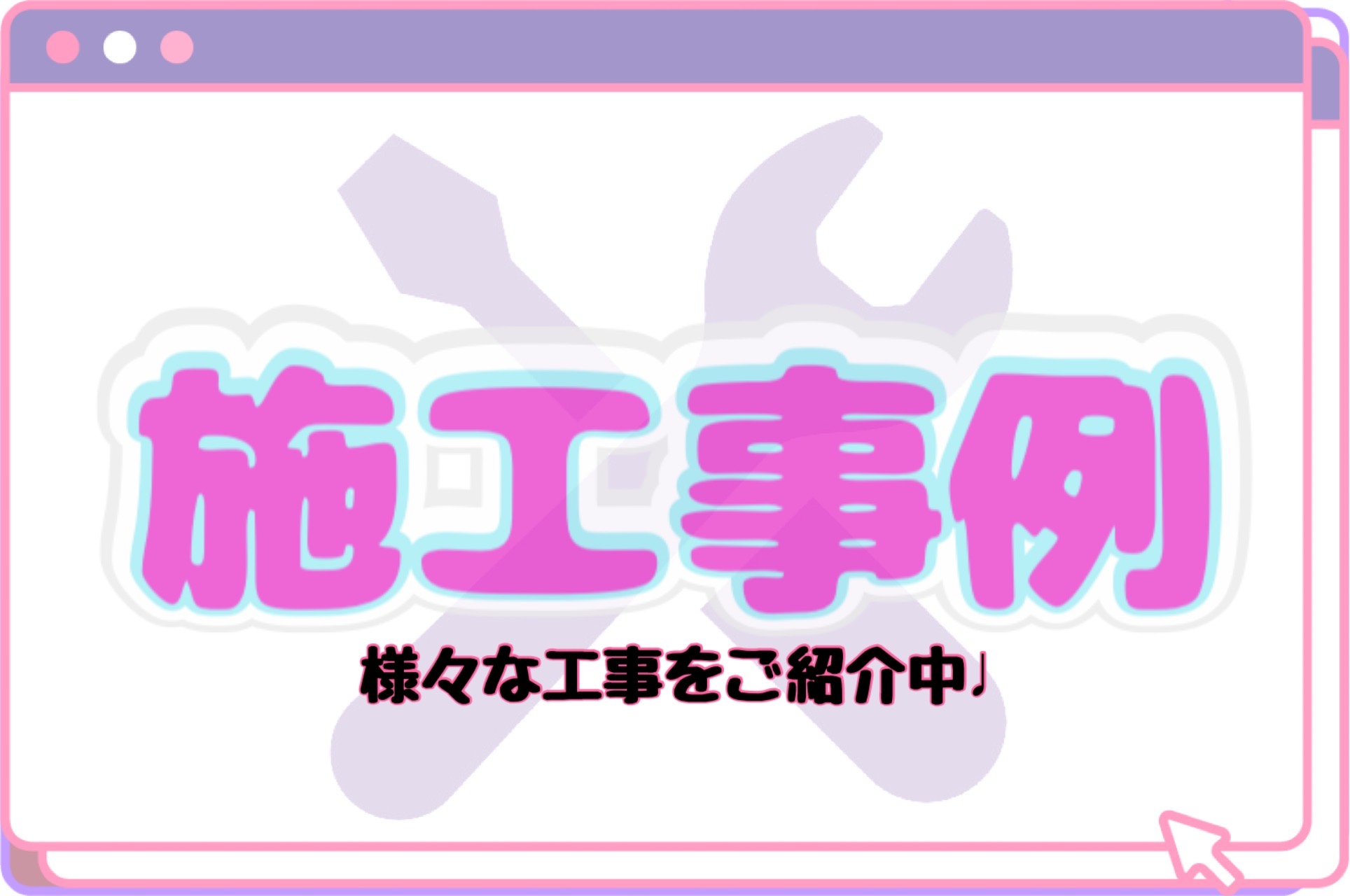
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん埼玉川口店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.